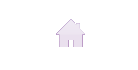サービス利用までの流れ
サービス利用までの流れ ①
日常生活を自分でおくるのが不自由であったり、不安があるなど、介護が必要と感じたら、
●保健福祉センター「きらく」に、ご相談ください。
介護支援専門員や保健師などが提供できるサービスなどをご説明します。
- 1 お気軽にご相談を
-
介護が必要と感じたら、まずは保健福祉センターにご相談ください。
たとえばこんな相談があります- サービスの利用が必要かどうか
- どのようなサービスがあるのか
- 家族の介護が大変になった
- 介護保険の利用方法がわからない など
- 2 状態を教えてください
-
日常生活で必要な機能など、ご本人の心身状態についてお伺いします。
ご相談・お話の結果
必要に応じて- 要介護認定申請のご説明
- 町で行っている福祉サービスや介護予防事業の紹介
- 3 要介護認定の申請を
-
介護保険のサービスを利用するために、認定を受けるための申請を行います。
申請に必要なもの- 認定申請書(保健福祉センターに備えてあります)
- 65歳以上 ...介護保険の被保険者証
- 40~64歳...医療保険の被保険者証

- ■申請についてのご注意
- 介護保険のサービスにつながる要介護認定はいつでも受けられます。
「65歳になったから」「自分の状態を知りたいから」と、とりあえず申請をする必要はありません。
急に介護が必要となった場合は、保健福祉センターにご相談ください。
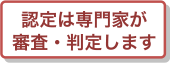
- 訪問調査や主治医の意見などを踏まえ、最終的に保健・医療・福祉の専門家等で構成する介護認定審査会で決められます。
3 申 請 |
保健福祉センター(保健福祉課介護保険係)に要介護認定申請書を提出してください。
|
|---|
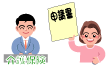

4 認定調査 |
保健師や介護支援専門員などの調査員がご自宅を訪問し、ご本人やご家族から心身の状況を調査します。
また、ご本人の主治医にも心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 |
|---|


5 審査・判定 |
|
|---|


6 認定・通知 |
審査会において下記の区分より認定し、その結果を通知します。
|
|---|

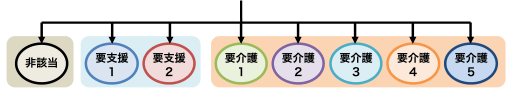
- ※通知は、申請後30日以内に届くことになっていますが、主治医意見書の作成に時間がかかることなどにより、30日を超える場合もあります。
- ※認定結果に納得できないときは、まず保健福祉センターにご相談ください。その上で納得できないときは、介護認定通知のあった日から3月以内に北海道の「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
要介護認定で非該当となった場合は・・・
要介護認定で「非該当」となると、自立生活が可能と判断され、介護保険適用のサービスを利用することはできません。
ただし、様似町では介護保険サービス以外に、移送・給食や自立者向けの訪問・通所介護事業、老人福祉寮などの福祉サービス、日常動作訓練や認知症予防などの地域支援事業を行っています。要介護認定で非該当となっても、日常生活上で何らかの問題を抱えていると認められる場合には、これらのサービスを利用することもできます。
サービス利用までの流れ ②
介護サービスの利用にあたっては、介護の専門家である介護支援専門員などがご本人の状態や要望を踏まえてケアプラン(サービス計画)を作成し、それに基づいたサービスが提供されます。
在宅でサービスを利用したい

■ケアプランの作成を依頼
(全額保険給付。自己負担はありません。)要介護(1~5)の人は居宅介護支援事業所、要支援(1・2)の人は地域包括支援センターに依頼してケアプランの作成を依頼・契約します。
■サービス担当者との話し合い 介護支援専門員又は地域包括支援センターの保健師等がご自宅を訪問し、ご本人の心身の状態や生活歴、家族の要望などを把握し、課題を分析します。
要介護の人には本人の力を引き出せるようなサービスを、要支援の人には目標を設定してそれを達成するための支援メニューを、ご本人・家族と実際にサービスを提供する担当者を含めて検討します。
町内の事業所は
- ●居宅介護支援事業所
さまに居宅介護支援事業所(社会福祉協議会)
居宅介護支援事業所 サニーサイド
勤医協浦河居宅介護支援事業所(浦河町)
様似町指定居宅介護支援事業所(保健福祉課) - ●様似町地域包括支援センター(保健福祉課)
ケアプランは、ご自身で作成することもできます。

施設へ入所したい
(要介護1~5の人のみ)
(特養は原則要介護3以上)

■介護保険施設へ申し込み
入所を希望する施設へ直接申し込みをします。施設をご存じない場合は、居宅介護支援事業所等において情報提供します。
入所・契約
入所が決定されると、施設と契約を結びます。
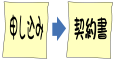

■施設ケアプランを作成
施設の介護支援専門員がご本人にあった施設ケアプランを作成します。
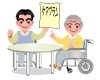

■ケアプランを作成
利用するサービスの種類や回数を決定し、ご本人又は家族の同意を得たうえで、ケアプランを作成します。
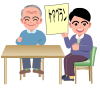
要介護1~5と認定された人は居宅介護支援
要支援1・2と認定された人は介護予防支援


■サービス事業者と契約
訪問介護や通所介護など、実際にサービスを提供する事業者と契約を結びます。


■在宅サービスを利用
ケアプランに基づいてサービスを利用します。
■施設サービスを利用
ケアプランに基づいてサービスが提供されます。
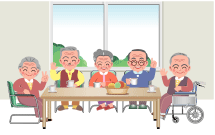
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?
介護支援専門員は、介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたって、次のような役割を担っています。
- ●介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。
- ●利用者の自立に向けたケアプランを作成します。
- ●実際にサービスを提供する事業者への連絡や手配などを行います。
- ●施設入所を希望する人に対して、情報提供や申し込みの支援を行います。